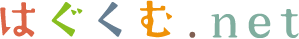このコラムでは、今現在使われている漢方処方の出典として、『傷寒論』および『金匱要略』の名前を何度も挙げてきました。今回からはしばらくこの『傷寒論』について考えてみます。
『傷寒論』が成立したのは、中国における後漢時代の末期から三国志で有名な三国時代にかけてであろうとされています。つまりはざっと1800年くらい前の時代にできたというわけです。『傷寒論』ははじめ、『傷寒雑病論』と称され、後に『傷寒論』および『金匱要略』に分けられました。まず雑病とは、急性熱病、今で言うところの感染症のようなもの以外の病気、つまり慢性疾患のようなものを総称する呼び方です。そして一方、傷寒とは、急性熱病、感染症のような疾患を指しています。したがって『傷寒論』は、以前も述べたように、現代でいう感染症マニュアルのような構成になっていますが、その病態に対する観察眼と、処方の絶妙さは脱帽モノで、本当に1800年も前に書かれたものだろうかと読む度に驚いてしまいます。
なんといってもその特徴は、病態を6つの病期・ステージに分けて、その病期毎に対処法を決めている点です。身体の外部からやってくる病原に対し、当初は身体の免疫がこれに対抗します。発熱したり炎症を起こしたり、熱のでるような状態であり、病原と免疫の戦いが起こる時期に相当します。これを3つに分け、三陽病期としました。すなわち、「太陽病・少陽病・陽明病」の3つです。次第に病気の勢いが増し、抵抗力が衰えてくる時期、これも3つに分け、三陰病期としました。熱はもはや目立たず、かえって冷えを感じるような病態で、「太陰病・少陰病・厥陰病(けっちんびょう)」としています。そしてこれらは、鍼灸でよく用いられる、経絡とも関係しているので、身体のどのような部位に病状があるのかも考慮しています。つまり、どこにどのような病変があって、それが時間の経過とともにどう変化していくのか、これに沿って治療方針を立てる戦略が、『傷寒論』には記されているのです。これは非常に画期的で、その後長い間現代に至るまで、漢方臨床の中心の考えとして輝きを失っていません。そしてその着眼点は、検査値や画像検索によって病気を理解しようとする現代医学がややもすれば忘れがちになる、「病態をしっかり経時的に細かく視る」、という重要な視点を、ふたたび強く思い起こさせてくれるものでもあります。
抗生剤や抗ウイルス薬など、漢方を使わずとも多くの感染症に対応することが現代医学では可能ですが、それらはいずれも病原体に対する薬であって、病原体にやられている身体のほうの状態は、必ずしも調整してくれはしません。したがって、病原体はやっつけたけれど症状は残るときや、その病原体そのものに対する薬が存在しないとき、なせる術が極端に少ないのです。漢方はそのようなときこそ、真の力を発揮します。身体がもつ免疫力や抵抗力、治癒力をうまく補助したり鼓舞したりして、様々な病気と戦う術をくれるのです。
《参考資料》
臨床応用傷寒論解説(大塚敬節・創元社)
傷寒論を読もう(髙山宏世・東洋学術出版社)
【文責】 三重大学附属病院漢方専門医・小児科専門医・医学博士 高村光幸