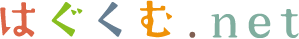今回は半夏瀉心湯(ハンゲシャシントウ)について考えてみます。この処方も葛根湯と同じ、『傷寒論』および『金匱要略』という古典に記載されています。分類でいえば、調和脾胃剤もしくは調和腸胃剤といって、胃腸のバランスをとる、というイメージでよいかと思います。現に『金匱要略』には、「吐きそうでお腹がごろごろ鳴って、みぞおちがつかえる者は半夏瀉心湯の証である」と書いてあります。
今回は半夏瀉心湯(ハンゲシャシントウ)について考えてみます。この処方も葛根湯と同じ、『傷寒論』および『金匱要略』という古典に記載されています。分類でいえば、調和脾胃剤もしくは調和腸胃剤といって、胃腸のバランスをとる、というイメージでよいかと思います。現に『金匱要略』には、「吐きそうでお腹がごろごろ鳴って、みぞおちがつかえる者は半夏瀉心湯の証である」と書いてあります。
みぞおちのことを漢方では心下(しんげ、あるいはしんか)と呼びますが、ここは身体の上下の気の運行の要所で、ここにいらないもの(邪)があるとつかえるような感じが出て、上下の気の運行に支障をきたしてしまいます。そのため、上には嘔吐、下には下痢の傾向が起こり、「吐きそうでお腹がごろごろ鳴って、みぞおちがつかえる」ということです。半夏瀉心湯の瀉心とは、この心下のつかえを取り去る(瀉とはそそぐ、流れる)という意味であり、つかえをとって気の上下の運行を正しく補正して、症状を改善させるというわけです。瀉心湯という呼び方がつく方剤はいくつかあって、生姜瀉心湯、甘草瀉心湯、三黄瀉心湯、附子瀉心湯、大黄黄連瀉心湯といったもので、黄芩(オウゴン)と黄連(オウレン)という生薬が基本的に配合されています。そのような方剤を芩連剤(ごんれんざい)とも呼びます(ただし大黄黄連瀉心湯には黄芩は含まれない)。医療用エキス製剤となっているのは半夏瀉心湯と三黄瀉心湯(サンオウシャシントウ)であり、瀉心湯のなかでは一般に半夏瀉心湯が最も有名です。
半夏瀉心湯には、悪心・嘔吐を治す代表的な生薬の半夏、心下のつまりをとる芩連の黄芩、黄連が配合されています。半夏はほとんどの場合、生姜や乾姜といったショウガと組み合わせて使われますが、本方剤にも乾姜が入っていて、健胃作用を持ちます。半夏や乾姜は辛く、黄芩や黄連は苦いのですが、辛み成分は開散の作用といって結したものなどを散じる、また苦み成分は降りるべきものを下に降ろす作用があると考えられ、これらの働きを「辛開苦降(しんかいくこう)」といいます。心下に結したつかえを解除して、下に流れるべきものを流す、というのがこの方剤の目的です。臨床的にはみぞおちのつかえ、悪心・嘔吐、食欲不振、腹鳴、軟便又は下痢といった胃炎や胃下垂、胸やけ、消化不良の症状に使います。口内炎にもよく用いられますが、そのメカニズムを漢方的な解釈で説明するにはスペースが足りなくなりましたので、この辺でこの回は終わりにします。
《参考資料》
医学生のための漢方医学基礎編(安井廣迪著・東洋学術出版社)
中医臨床のための方剤学(神戸中医学研究会編著・東洋学術出版社)
《写真提供》
株式会社ツムラさんのご厚意による
【文責】 三重大学附属病院漢方専門医・小児科専門医・医学博士 高村光幸