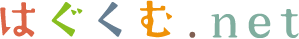ようやく涼しくなってきました。今年は早くもRSウイルスが大流行してきているようですが、相手はウイルスですので原則抗生剤が効かず(抗生剤は細菌に対する薬です)、対症療法(根治ではなく症状を緩和する治療)にて重症化させないことが基本の病気です。そもそも、小児がかかるほとんどのかぜ様の症状は、ウイルスが原因なので抗生剤は不要です。ところが、医師の多くは、「念のために」、「重症化させないために」、「親の安心のために」、ほぼ不要と思いながら、軽症の感染症に抗生剤などを処方していることが、日本小児科学会の会誌をみても事実であると言えます。抗生剤による副反応の恐れや耐性菌の出現について、医師のほうも十分承知して、理解の上で敢えて処方している理由は、多くの軽症に紛れて存在する重症感染症に対してのリスク回避意識と、保護者がもつ「薬を、特に抗生剤を飲まさないと治らない」という思い込みに応えざるを得ない、という背景もあるようです。
ようやく涼しくなってきました。今年は早くもRSウイルスが大流行してきているようですが、相手はウイルスですので原則抗生剤が効かず(抗生剤は細菌に対する薬です)、対症療法(根治ではなく症状を緩和する治療)にて重症化させないことが基本の病気です。そもそも、小児がかかるほとんどのかぜ様の症状は、ウイルスが原因なので抗生剤は不要です。ところが、医師の多くは、「念のために」、「重症化させないために」、「親の安心のために」、ほぼ不要と思いながら、軽症の感染症に抗生剤などを処方していることが、日本小児科学会の会誌をみても事実であると言えます。抗生剤による副反応の恐れや耐性菌の出現について、医師のほうも十分承知して、理解の上で敢えて処方している理由は、多くの軽症に紛れて存在する重症感染症に対してのリスク回避意識と、保護者がもつ「薬を、特に抗生剤を飲まさないと治らない」という思い込みに応えざるを得ない、という背景もあるようです。
保育園や幼稚園では、ちょっと発熱すると元気でも子どもは親元に帰されます。そして夕方や夜間救急に、「発熱」を主訴に受診します。実はどのような感染症でも、発熱初期だけでは他の症状や所見が目立たず、フォーカス(感染している場所、たとえば鼻やのどなのか、気管支や肺なのか、尿路系なのか、中枢神経系なのか、など病巣がどこかということ)が不明な場合が多く、多くの軽症のなかに稀に紛れ込んでいる重症感染症などと区別がつかない場合が多いのです。ですから、子どもの全身状態などをきちんと医師のほうは調べますが、発熱以外に問題がなさそうであれば、薬は不要でそのまま帰宅させても本当はよいところを、万が一、あるいは薬なしだと保護者の不満がきかれるので、念のため、抗生剤を出さざるを得ない状況になっている場合が多くみられます。これは保護者のほうに、発熱が子どもにとって悪いことだ、という認識があるように思えます。熱はなくても、咳や鼻水があって、元気だけど病院に連れてくる、という場合も咳や鼻はよくないものだ、という意識があるようです。そして結果、薬が出されると言うことはそれが必要なんだ、という発想になって、症状がでたら病院にすぐ行く、というサイクルができあがってしまいます。しかし、本当に熱や咳や鼻水はでていてはいけないのでしょうか。
子どもの頃に比べて、大人はそれほど熱を出しません。それは大人が小さいときにいろいろな感染症と闘って、免疫をつけてきたからです。熱がでるのは、入り込んできた病原体に対して体が抵抗しているためです。闘いに慣れていればすぐ排除できるので、高い熱がでるところまで頑張らなくてもいいのです。逆に体の抵抗力がなさ過ぎると、老人のように熱がでにくい、ということもあります。子どもの熱は体を護るための防御反応の現れなのです。加えて咳や鼻水も、入り込んできた病原体を排除しようとして体がわざと出しているのです。それなのに解熱剤で必死に熱を下げたり、咳止めや鼻水止めを飲ませたりすることが、果たして子どものためなのでしょうか。先に挙げた小児科学会の文献でも、ほとんどの小児の感染症において、抗生剤のみならず、咳止めや鼻水止めと称して処方されている薬のほとんどが不要ということが示されています。実際の臨床で自分も不要と割り切れているかという自戒も込めて、改めて小児に対する投薬の意義を考えることが必要かと思います。それは、漢方薬の使い方につながる考えがあるからです。
解熱剤は熱を下げるかも知れませんが、原因の病態を改善はしません。親が体温計の数字を見て安心するだけです。せっかくの闘いに水を差しているのに等しいものです。漢方では、発熱は抵抗力である正気と、病原体である邪気の闘い、邪正相争(じゃせいそうそう)が起こっているために発熱すると考えます。そこでそれをサポートするための治療を行うわけです。鼻が出る場合、漢方を飲ませると一旦ひどい鼻水がでて、その後すっきりする、ということも見られます。敢えて悪いものをいっぺんに出させてしまうのが漢方です。西洋薬は咳や鼻を出す指令を無理矢理ストップさせているに過ぎないので、見かけ上は止まったとしても、体の中の病原体にとっては、返って都合のいいことをしているだけなのかも知れません。じゃあどうして抗生剤や咳止めを飲んでいたら症状が治まるのでしょうか。ほとんどは体の力が勝って、自然に治っているだけでしょう。そこを証明するのは、西洋薬も漢方薬も、これから必要になってくる話でもあります。
文責 三重大学附属病院漢方外来担当医・小児科専門医 高村光幸
《参考文献》
日本小児科学会雑誌2010年9月号総説
「小児プライマリーケアにおける抗菌薬の適正使用について」(西村龍夫・日本小児科学会)
《写真提供》
株式会社ツムラさんのご厚意による